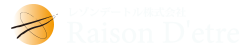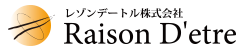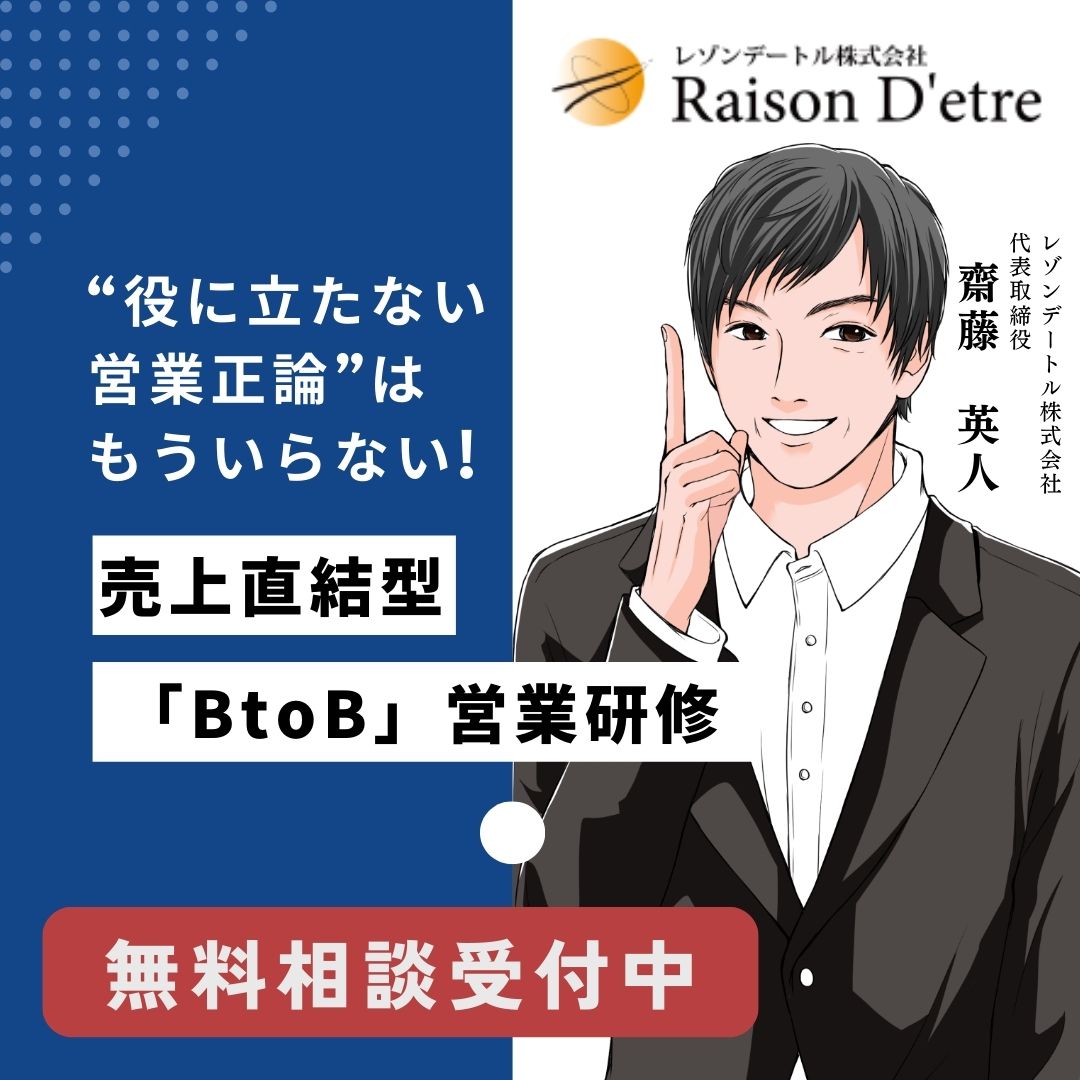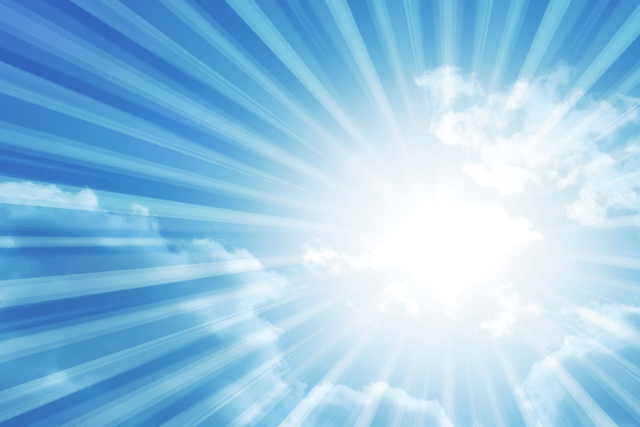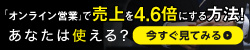本日の記事の見出し
正しい目標設定法は「結論」が出ています。
今日は
「行動が生まれる正しい目標設定」
というテーマに触れてみたいと思います。
<index>
①あなたはどっち?目標はできるだけ高く設定したほうが良いと思う?
■あなたはどっち?目標はできるだけ高く設定したほうが良いと思う?
ビジネスパーソンであるあなたには必ず
「目標」
が設定されています。
営業であれば予算達成
開発部門であれば納期
人事部門であれば採用人数
仕事と役割によって異なりますが
「必ず目標設定」
はされていることでしょう。
目標設定の際に上がる疑問があります。
A「目標は高く設定したほうが良いのか?」
B「確実に達成できるものが良いのか?」
自分で立てる目標であれば、本人の考えで設定されています。
また責任者の考えで、チームの目標も決まっています。
目標設定のダメな例を見てみましょう。
例えば売上目標でよく見かける例です。
多くの企業がたどり着く結論に
「昨年の数字に10%プラスする」
というものがあります。
昔から
「110%ルール」
などと言っていますが、合理的な目標設定ではありません。
大きな企業でも
「目標設定の指針」
で用いられている間違った方法です。
ではなぜ間違った方法なのでしょうか?
さらに良くしようとする合理的な目標ではないのでしょうか?
間違いの理由は
「マイナスの行動」
がつくられる可能性が高いからです。
例えばノルマの厳しい会社で
「数字の進捗が非常に順調な営業」
がいたとします。
さて彼は残り3か月で、何を思うでしょうか?
恐らくは
「これ以上売上をあげたら、来季の数字が厳しくなる」
と考え、意図的に契約をしないという行動が生まれます。
本来、営業は
「お客様の価値を創造する」
ことが役割です。
しかしこの営業が期末に見ているものはお客様ではありません。
一方で高すぎる目標も
「スタート時点から行動が消える」
ことになりそうです。
期初の時点で
「こんな目標無理に決まっているじゃないか」
と言って動機付けが失われています。
ではどんな目標設定をすれば
「正しい行動が創られる」
のでしょうか?
実は目標設定の議論については様々な研究により
「科学的に結論」
が出ています。
■目標設定には3つの項目を掛け合ったもの
目標設定の様々な研究の中から、2つピックアップしてみましょう。
まず1つ目は
「心理学者アトキンソンの理論」
をご紹介します。
アトキンソン理論は人の動機付けは
「3つの項目の掛け合わせによる」
と定義をしています。
「動機づけの強さ 3つの項目」
1 本人の達成動機の強さ
2 成功の主観的確率
3 成功報酬の価値の高さ
上記3つを掛け合わせたものです。
ここでご質問です。
アトキンソン理論に基づいたとき
「一番コントロールしやすい」
のは3つのうちどれでしょうか?
答えは
「2 成功の主観的確率」
です。
本人の達成動機の強さはコントロールできそうにありません。
また成功報酬についても上限といった制限があります。
ただし
「成功の確率」
については、ある程度の予測やコントロールができる項目です。
ではどの程度の確率で考えればよいのでしょうか?
■人の行動が生まれる最適な目標値がついに明らかに!
最適な確率を示す
「もう1つの研究結果」
があります。
「輪投げの成功」
という実験です。
【輪投げの実験】
小学生を集めて輪投げをしてもらう
様々な距離から投げてもらう
投げる前にどのくらいの確率で成功するかを聞く
一定時間自由に輪投げをさせて観察する
すると
「一番投げられた距離」
が明らかになりました。
つまり
「一番行動が創られた距離と成功確率」
ということです。
では一番少なかった(行動が創られなかった)2つから見てみましょう。
・最も簡単だと思う距離(達成確率が高いと思う距離)
・最も難しいと思う距離(達成確率が低いと思う距離)
上記の2つからは投げられた回数が
「一番少なかった」
という結果が出ました。
では投げられた回数で
「一番多かった」
のはどのくらいの確率なのでしょうか?
一番多かったのは
「50%の成功確率」
と思われていた距離からです。
その後、成功した距離ごとにグループに分けて競争をさせました。
グループ分けをしても
「50%の成功確率」
のチームの結束力が一番高かったという結果が出ました。
つまり
「確実に成功する」「まず失敗する」
とわかっている目標では行動は創られないということです。
一番行動が創られるのは
「50%成功する目標」
です。
目標を設定する際には
「適度な難易度」
を頭に入れてから考えると良いですね。
自分自身の目標設定
部下への目標設定
チームの目標設定
上記のいずれにも適応できるものです。
目標設定に重要なのは
「50%の成功率」
と断定してかまいません。
目標設定の最適値の
「結論」
です。
次の目標設定の際には
「50%」
を軸に定めましょう。
また50%という数字を導いた根拠として
「プレゼンテーション」
でこの記事の内容を使ってください。
人の行動の多くは科学的に明らかになっています。
ノーベル賞を受賞した素晴らしい学者たちが
「人生をかけて解明した叡智」
です。
私の提唱している
「行動創造理論」
は人類の叡智を営業とマネジメントに適用した理論です。
科学のチカラで
「売上を創る理論」
です。
■行動創造理論は脳のメカニズムを先回りする
私の提唱する行動創造理論は
「科学を基軸とした営業理論」
です。
脳のメカニズムに基づいた行動を体系化したものです。
-
脳科学
-
認知心理学
-
行動経済学
上記のノーベル賞を取った研究や知見を「営業行動」に体系的に落とし込んだものです。
科学を基軸とした営業技術を身につけ、売上が飛躍的に伸びるプログラムです。
-
営業研修
-
マネジメント研修
-
能力開発トレーニング
「もっと売上に繋がる営業研修を実施したい」
「確実に営業力が上がる営業研修はないか」
と一度でも思ったことのある方は、ぜひ触れてもらいたいプログラムです。
営業で成果を出すには
「人の本能の行動に合わせる」
だけです。
成約率が50%向上した
新規案件数が10倍に増えた
たった1か月で売上が4.6倍になった
上記の成果を導いたプログラムにご興味をお持ちの方は、ご連絡をいただければと存じます。
売上に関する課題はすべて解決できるようになるでしょう。
今日は「行動が生まれる正しい目標設定」というテーマに触れてみました。