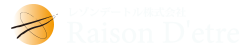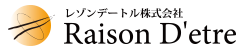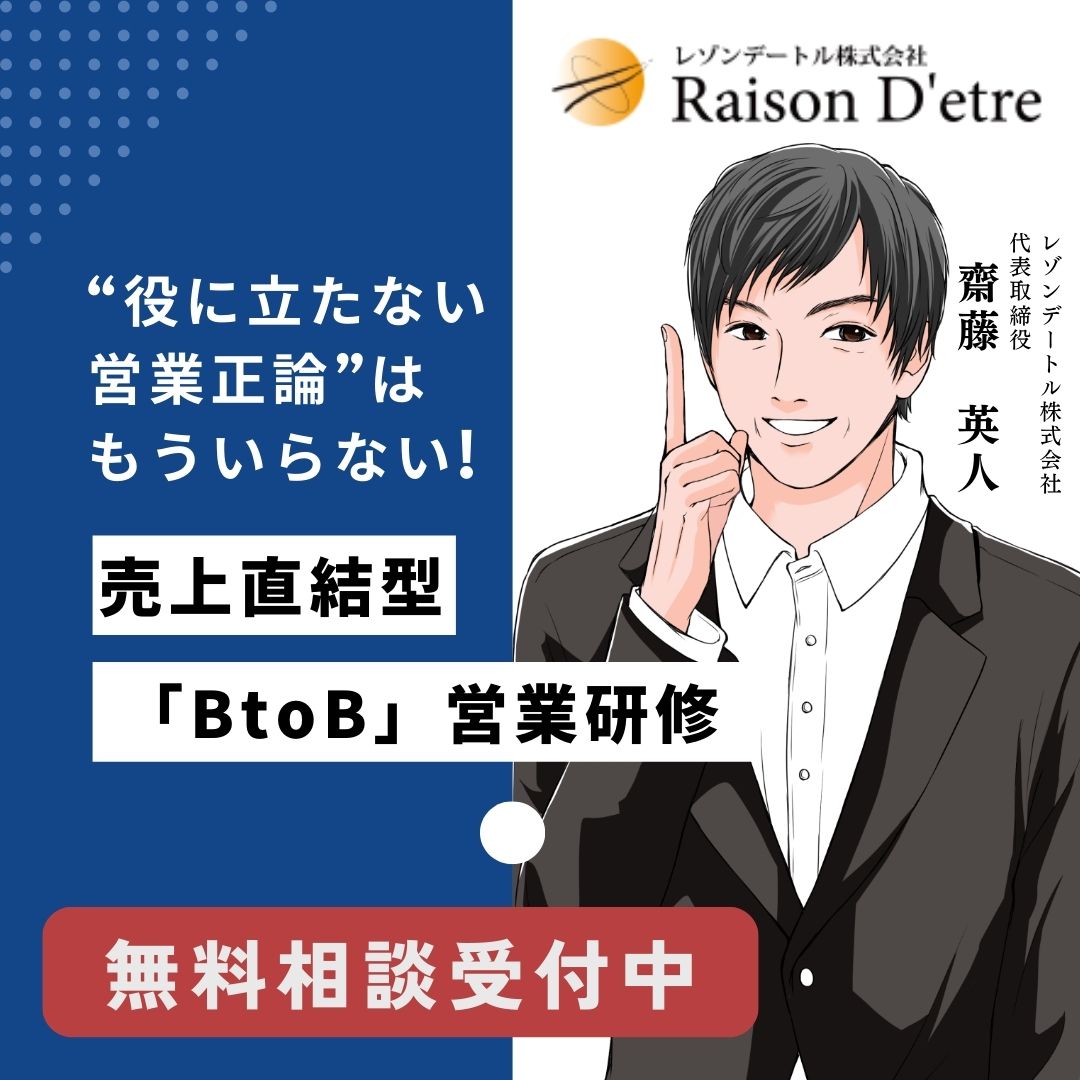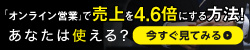嫌われた和尚さんが、なぜ好かれるようになったのか?
大人気のビジネス寓話シリーズをお送りいたします。
今日のお話は
「たぬきの手習い」
です。
どんな教訓があるのでしょうか?
—————————-
昔、山のすそ野にある寺に
「源哲」
という和尚がやってきました。
さっそく村の人たちは挨拶するため、寺にやってきました。
しかし屋根の上で酒を飲んでいる和尚さんを見つけ、あきれて声もかけずに帰って行きました。
村の人には相手にされなかった源哲でしたが
「面白そうな和尚さんだ」
と裏山に住む子たぬきにはすっかり気に入られてしまいました。
タヌキは人間の子供に化けて源哲に声をかけました。
子供好きの源哲は
「よし読み書きを教えてやろう」
といって、タヌキたちは読み書きを教わることになりました。
源哲と子タヌキたちが楽しそうなのを見て
「村の子供たちも親に内緒で」
習いに来るようになりました。
ある日のこと、手習いのお礼にと、村の子どもたちは近くの川で獲った魚を和尚さんに差し出しました。
子タヌキたちも何かお礼をしようと話し合い、雨の日に和尚さんの代わりに酒を買いに行くようになった。
ところが、酒屋の主人が
「雨の日にだけやって来る子供たちを怪しい」
と思います。
ある雨の夜、こっそりと子供たちのあとをつけていきました。
寺に入ったところで子供たちにしっぽがある事に気が付き、持っていた傘で思いっきり子供たちを殴りつけました。
子タヌキたちは正体を現し、泣きながら山に逃げ帰り二度と姿を現さなくなりました。
源哲は
「あの子たちがタヌキだったとは。わしを喜ばそうとしたばっかりに…。」
と悲しみました。
しかしこのことで
「源哲が子供想いのやさしい人」
と知ることになり、人が行き来することになりました。
—————————-
このお話の教訓はどこにあるでしょうか?
まず人は
「悪い情報に目が行く」
ことを表しています。
挨拶に行った村人は
「昼間から酒を飲んでいるからだらしない」
という悪い情報を目にしました。
悪い情報に目が向けられるのは
「生き物の本能の動き」
です。
なぜなら悪いものを察知しなければ、生存競争で勝てないからです。
普段周りの人の
「悪いところばかり目につく」
というのはあなたの性格が悪いわけではありません(笑)
このお話の和尚さんは
「村人にだらしない人」
と思われていました。
人間の脳では
「悪い印象による先入観」
は容易に形成されます。
しかもそれは
「時間の経過とともに膨れていく」
という厄介なものです。
そもそも子供たちが
「内緒」
で和尚さんのところに来ていたのはなぜでしょうか?
内緒で来ていた理由は
「親たちの反対」
があったからです。
親たちの和尚さんへの評価は
「悪いまま」
で更に膨れていきました。
恐らくこのままでは
「和尚さんは村人から嫌われたまま」
だったでしょう。
本来、人間関係を上手く行う秘訣は
「良いことを追い求めるより、悪いことを避ける方がはるかに大切である。」
という研究結果があるくらいです。
本来、悪い評価はなかなか覆りません。
しかも時間が経てばたつほど、ネガティブな気持ちはふくらみます。
ではなぜそれが変わったのでしょうか?
ここが、一番の教訓です。
■1つが良ければ全部が良くみえる「ハロー効果」
変わった理由は
「ハロー効果」
が働いたからです。
親にとって
「命よりも大切な子供たち」
が慕っていた。
そして
「子供たちのために」
悲しんでくれた和尚。
子供たちを通じて、和尚さんの印象が良く見えたのです。
そして
「1つの印象が良ければ、他の能力も優れている」
と認識をするハロー効果が働きました。
最後の評価は
「優しい和尚さん」
となって親しく行き来するようになりました。
■昔ばなしやことわざの根拠にも「行動創造理論」がある
この寓話には3つの行動科学が詰め込まれていました。
①人は悪い情報に目が行く
②ネガティブな情報は時間と共に膨れていく
③ハロー効果ですべてが良く見えるようになる。
昔ばなしの教訓からも
「行動創造理論」
を学ぶことができます。
様々な寓話やことわざは
「科学的に根拠がある」
ことばかりです。
アンテナを高くしたり、角度を変えることで
「物事の本質」
をとらえることができます。
普段は無意識のうちに
「物事を見ている」
ことが多いはずです。
なぜなら人の判断のほとんどは
「無意識のうちに行われているから」
です。
1日に1回だけでも
「違った視点で見る習慣」
を作るだけで、あなたの行動は大きく変化するでしょう。
1つだけでも変われば
「和尚さんのように、評価が大きく変わる」
かもしれません
今日はビジネス寓話シリーズ
「タヌキの手習い」
をお送りいたしました。