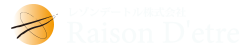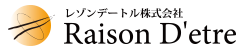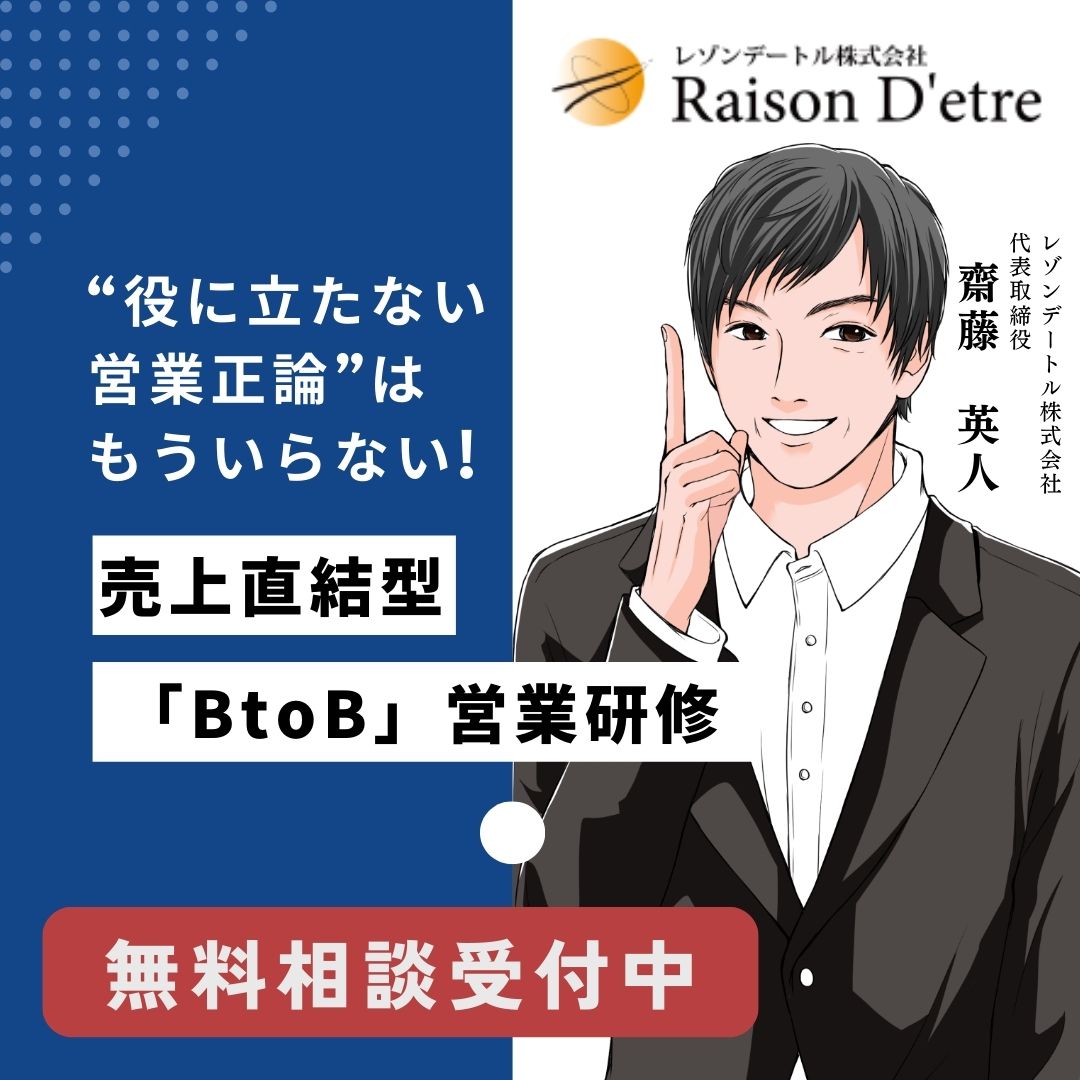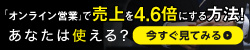本日の記事の見出し
ほとんどの大人が解けない足し算とは?
今日は
「大人の足し算」
というテーマに触れてみます。
<index>
■あなたは大人の足し算の答えを出すことができますか?
一番簡単な算数の計算です。
「1+1」
の答えは何ですか?
答えは
「2」
です。
しかし大人の足し算は
「単純ではない」
といえるでしょう。
大人の足し算とは
「ビジネスにおける足し算」
のことです。
ビジネスにおいては
「単純に想定通りの答えにならない」
ということです。
■計算式の「1」が持つ意味とは何か??
この「1」というのは
「企業の持つ資源」
と言いかえられます。
ヒト
モノ
カネ
情報
企業がそれぞれ持つ
「内部資源」
があげられます。
政治的環境
経済環境
お客様の動向
競合の動向
さらには上記の
「外部資源」
があげられます。
この資源1つ1つが
「1」
という数字になります。
内部環境に変化がなくても
「法制度が変わりプラスに働く」
「競合が失策をした」
ということで変化は絶えず生まれています。
今はコロナで生活が大きく変容しているので
「外部資源の変化」
が大きいですね。
そのことから
「1」は⇒「2」にも「3」
にもなります。
しかし逆に
「1+1=1」
ということもあり得ます。
■ほとんどの企業の計算式の実態は「1+1=1」
あなたの組織も
「内部資源の活用」
ではプラスにならないケースのほうが多いのではないでしょうか?
販促施策を試みるも成果がでなかった
インターネット広告を出したが成果が出なかった
オンラインセミナーを開催したが集客ができなかった
こ上記の結果は
「1+1=1」「1+1=0」
といえるのかもしれません。
別の例でも見てみましょう。
10人にいる営業チームがあったとします
「10人全員が力を発揮できている」
と言い切れる組織はどれだけあるでしょうか?
「10+10=10」
にもなっていない組織もあるのではないでしょうか?
「10+10」
これを25や30にするにはどうすればよいでしょうか?
まずは
「メンバー特性を把握する」
ここからスタートです。
■将棋やチェスで考えることが、なぜ人だとできないのか?
メンバーそれぞれに
「強み弱み」
があるはずです。
メンバー特性を
「把握して組み合わせる」
ということがマネジメントです。
なんでも平均点でそつなくこなすメンバー
ヒアリング能力は飛びぬけて高いメンバー
資料作りが得意なメンバー
様々なタイプがいると思います。
このメンバーに
「同じミッションを与える」
というのは効率的でしょうか?
それとも
「組み合わせる」
ほうが効果的でしょうか?
将棋やチェスを思い起こしてみてください。
コマには
「様々な特徴を持った資源」
があります。
間違いなく
「資源を組み合わせて有効的に活用する」
ことができるほうが強いですよね?
あまり人のことを
「駒」
に例えるのは好きではないですが、わかりやすいのであえて引き合いに出しました。
「資源と「足し算」
2つの視点で見てみましょう。
「1+1=3」 を実現するにはどうしたらよいか。
経営陣が真剣に考えた時に
「戦略」
になります。
管理職が真剣に実行しようとした時
「マネジメント」
になります。
「1+1=3」
は結果を求めるものはありません。
「正しい行動」
を求めるものです。
「正しい行動が創られる環境を整える」
とすれば、必ず結果が生まれます。
特に市場の変化が大きい今は
「行動マネジメント」
への転換が必須です。
【行動マネジメントの効果】
1:短期間でリーダーを養成することができる。
2:従来の戦略戦術を、融合して活用することができる。
3:売上を伸ばすマネジメントの仕組みが構築ができる。
4:トップ社員のパフォーマンスを維持、継続ができる。
5:平均的な社員をトップクラス社員に伸ばすことができる。
6:平均以下の社員をアベレージ以上に伸ばすことができる。
7:セルフマネジメントにも応用できる。
詳しい導入方法を知りたい方は、下記よりご連絡をください。
■行動創造理論は脳のメカニズムを先回りする
私の提唱する行動創造理論は
「科学を基軸とした営業理論」
です。
脳のメカニズムに基づいた行動を体系化したものです。
-
脳科学
-
認知心理学
-
行動経済学
上記のノーベル賞を取った研究や知見を「営業行動」に体系的に落とし込んだものです。
科学を基軸とした営業技術を身につけ、売上が飛躍的に伸びるプログラムです。
-
営業研修
-
マネジメント研修
-
能力開発トレーニング
「もっと売上に繋がる営業研修を実施したい」
「確実に営業力が上がる営業研修はないか」
と一度でも思ったことのある方は、ぜひ触れてもらいたいプログラムです。
営業で成果を出すには
「人の本能の行動に合わせる」
だけです。
成約率が50%向上した
新規案件数が10倍に増えた
たった1か月で売上が4.6倍になった
上記の成果を導いたプログラムにご興味をお持ちの方は、ご連絡をいただければと存じます。
売上に関する課題はすべて解決できるようになるでしょう。
今日は「大人の足し算」というテーマに触れてみました。